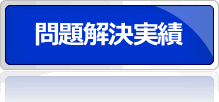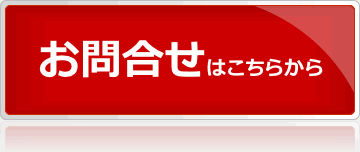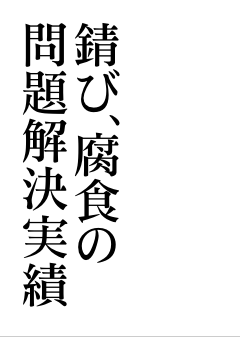- ホーム
- 錆び、腐食の問題解決実績ブログ
- 津波避難タワーの錆び事例に学ぶ ─ 防食と耐食の違い
津波避難タワーの錆び事例に学ぶ ─ 防食と耐食の違い
Posted on 2025.09.08
1. 10年で使用中止となった避難タワー
千葉県匝瑳(そうさ)市の海岸に建てられた津波避難タワー(2015年完成、総工費約7,800万円)が、設計耐用年数31年とされていたにもかかわらず、わずか10年で腐食が進み、2024年に使用中止となったことが報道されました。
画像は読売新聞オンラインの記事より引用
市の説明によれば、このタワーにはステンレスフレークを含む塗料が採用され、「錆びにくい新技術」として施工されたといいます。
しかし実際には、設計寿命を大きく下回る形で腐食が進行してしまいました。ここから見えてくるのは、「防食」と「耐食」の違いを正しく理解することの大切さです。
2. 防食と耐食の違い
同じ「錆を防ぐ」でも、その仕組みは大きく二つに分かれます。
-
防食:鉄より卑な金属(亜鉛・アルミなど)が犠牲的に溶けることで鉄を守る。
例:溶融亜鉛めっき、Zn-Al合金溶射、ジンクリッチ塗料。 -
耐食:素材や皮膜そのものが腐食に強い性質を持ち、外部環境を遮断する。
例:ステンレス皮膜、アルミ皮膜、ステンレスフレーク塗料。
防食は「犠牲防食」、耐食は「バリア効果」と整理すると分かりやすいでしょう。
3. なぜステンレスフレーク塗料では足りなかったのか
ステンレスは鉄より「貴」な金属です。電位的に犠牲防食の役割を果たさないため、鉄を守るには不向きです。塗料としては高いバリア性能を持ちますが、ひとたび膜に傷や不均一があれば、そこから腐食が一気に進行するリスクがあります。
つまり、ステンレスフレーク塗料は「耐食性の皮膜」としては評価できますが、「防食の代替」としては不十分なのです。
防食目的ではステンレス溶射は使わないのも、同じ理由からです。
ちなみに、膜厚の管理も重要です。
塗膜の厚みは全体的に十分あったのかどうか、ピンホール・ブローホールの類いはなかったのか、も気になるところではありますが。
4. 匝瑳市の3基のタワーの違い
この点を裏付けるように、匝瑳市が整備した3基の津波避難タワーのうち、ステンレスフレーク塗料を使ったのは今回の1基のみでした。
残る2基は溶融亜鉛めっき塗装が採用されており、こちらは犠牲防食の仕組みに基づくものです。
同じ市内で施工時期も近いにもかかわらず、塗装仕様が分かれていたことは、「防食」と「耐食」の意味の違いが設計段階で十分に理解されていれば、選択は異なった可能性を示しています。
ちなみに、溶融亜鉛めっきの場合は15年程度で錆が出てくる可能性があるため上塗塗装が必要です。また、温度が高いためひずみが出る可能性が高いなど、気になる点はいろいろありますがここでの主題ではないので触れないでおきます。
弊社の溶融亜鉛めっきに関するブログは下記をご覧ください。
→https://www.100nensabinai.jp/case_study/2025/04/post-84.html
5. 今回の事例が示すもの
この事例から学べるのは、新しい塗料を使えば錆びない、という単純な話ではないということです。
重要なのは、
-
防食と耐食というアプローチの違いを理解すること
-
環境(特に海岸部の塩害)に応じた適材適所の工法を選ぶこと
-
維持管理まで含めた長寿命化の設計を行うこと
です。
まとめ
ステンレスフレーク塗料は優れた耐食塗料ですが、「防食」の代わりにはなりません。匝瑳市の3基のタワーの仕様の違いは、それを象徴的に示しています。
私たち新免鉄工所は、亜鉛-アルミ合金溶射などの防食技術を軸に、環境に最適な工法を提案し、公共インフラの長寿命化に貢献してまいります。
参考文献・出典
-
テレ朝NEWS「津波避難タワーさびだらけ 耐用31年が10年でボロボロ 建て替え困難 千葉・匝瑳市」(2025年9月報道)
-
匝瑳市公式ホームページ「津波避難タワー」整備概要(塗装仕様の記載)
タグ一覧
- 100年防食 金属溶射 防食溶射 ,
- 15トン ,
- すべり止め ,
- めっき ,
- アルミナブラスト ,
- アルミニウム ,
- アルミニウム・マグネシウム溶射 ,
- アルミニウム溶射 ,
- アーク溶射 ,
- インペラ ,
- ガスフレーム溶射 ,
- キュービクル ,
- ギヤ ,
- グリットブラスト ,
- グリッドブラスト ,
- グレーチング ,
- シリンダー ,
- ジンク塗装 ,
- スケール除去 ,
- ステンレス ,
- タンク ,
- パイプ ,
- ブラスト加工 ,
- マスキング ,
- ライニング ,
- 上塗 ,
- 亜鉛・アルミニウム溶射 ,
- 亜鉛溶射 ,
- 低圧 ,
- 動画 ,
- 古物 ,
- 和歌山 ,
- 圧力 ,
- 塗装下地 ,
- 大型乾燥炉 ,
- 大型構造物 ,
- 小物 ,
- 尼崎工場 ,
- 摩擦係数向上 ,
- 放熱性 ,
- 旧塗膜除去 ,
- 歪み ,
- 水管橋崩落 ,
- 溶射 ,
- 焼付塗装 ,
- 焼鈍 ,
- 狭隘部 ,
- 異常な腐食 ,
- 短納期 ,
- 紛体塗装 ,
- 縞鋼板 ,
- 耐熱 ,
- 薄板 ,
- 表面積増加 ,
- 表面粗さ ,
- 補修 ,
- 超厚膜塗装 ,
- 部分加工 ,
- 配電盤 ,
- 重量物 ,
- 錆び取り ,
- 錆止め塗装 ,
- 長尺物 ,
- 階段 ,
- 13Cr
![問題解決実績 [CASE STUDY]](https://www.100nensabinai.jp/case_study/img/title_caseEntry.jpg)